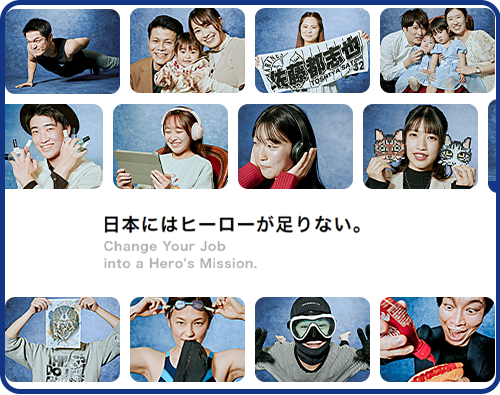2025年に新卒でドットラインへ入社した魏(ウェイ)さん。現在は「ドットホーム(医療対応型障がい者グループホーム)」で生活支援員として活躍をしています。出身は中国、学生時代はアメリカで過ごしていた魏さんが、なぜ日本での就職を選んだのか。きっかけになったエピソードをはじめ、大変だったこと、強みになっていること、そして、ご自身と同じく日本での就職を目指す留学生に向けてのアドバイスなどを伺ってきました。
💡ドットホーム(医療対応型障がい者グループホーム)とは
医療的ケアが必要な障がいを持つ18〜65歳の方が、24時間365日の看護体制のもとで安心して地域生活を送るためのグループホーム。各自に個室があり、建物は一般的なアパートと同様の造りになっている。
専攻していた社会学が日本に来るきっかけになった

– 就職するまでの経歴について教えてください
私は中国で生まれ、高校に進学するときに家族の勧めでアメリカへ渡り、大学もアメリカで学びました。社会学を専攻していたこともあり、さまざまな国の文化や社会を学ぶなかで、日本にも興味を持つようになりました。幼いころから日本のゲームやアニメが好きだったこともあり、大学3年生のときに上智大学への交換留学で日本に来ました。
新型コロナウイルスの影響で留学は半年ほどで終わってしまいましたが、もっと日本について学びたいと思い、大学卒業後は日本の大学院に進学。大学院では、中国と日本の文化の融合をテーマに「メディア(ゲーム文化)の社会学的分析」を行いました。
– 日本で就職をしようと思った理由は?
在学中に日本語能力試験(N1)を取得し、自分のスキルを試したいと思ったからです。家族も「やりたいことをしなさい」と背中を押してくれました。また、日本はとても住みやすく、安心して暮らせると感じました。
最初は論文でも扱っていたゲーム関係の会社を目指していましたが…
ここで大きな問題がありました。
– それはどんな問題?
日本の就職活動の時期が分からず、動き出した時には気になる会社の選考はすべて終わっていたんです。
周りの助けを借りながら、慌てて求人媒体に登録し、さまざまな会社の説明会に参加しました。その中の1つがドットラインでした。社会問題への取り組みや『地域の「困った」を「ありがとう」に変えるⓇ』という言葉に、とても魅力を感じました。事業の内容にも社会学で学んできたこととの繋がりがあり、これまでの知識を活かした貢献ができるかもしれないと感じて入社を決めました。
―内定から入社までの期間に会社からのサポートはありました?
ビザ申請の具体的手順を書面でもらえたり、とても助かりました。
また、千葉について何も知らなかったので、住まい探しや通勤方法について相談に乗ってもらえたのも心強かったです。引っ越し手当の対象エリアを踏まえて相談に応じてもらえたので、費用面でも安心できました。
すれ違いを減らす。文化の違いは拠点ルールに追加

– 配属先と今の仕事について教えてください。
成田にあるグループホームに配属され、利用者様の生活支援や見守りを担当しています。
– 仕事はどうですか?
最初は夜勤に慣れるのが大変でしたが、今は順調です。夜勤は月にだいたい7~8回ですが、日勤→夜勤→夜勤明けというリズムに慣れてきたのでもう心配ありません。
–ほかに大変だったことは?
やっぱり最初は、日本語でのコミュニケーションに自信がなかったです。「話は通じるかな?」「内容を理解できるかな?」なんて、ずっと考えていました。でも、全然大丈夫でした。一緒の拠点にいるクルーたちは相談しやすく、すぐに安心できました。
みんなと同じ仕事をしたいですし、理解できないことを理由に特別扱いされたくなかったので「昨日よりもできるようになろう」と、1つずつできなかったことを解決しながら頑張っています。
–文化の違いなど感じた場面はありましたか?
日常的にあるのは、食事の準備です。中華や洋食には慣れていても、和食では初めて見るものも多く、盛り付け方を教わることがあります。
また、漢方(薬)の準備も印象的でした。
中国では漢方は絶対に溶かして飲ませます。でも、日本ではそうじゃない。そして、グループホームでは、利用者様によっても対応が違う。準備をしているときに隣にいたクルーから「なんで溶かしているの?」と声をかけられて、そこで初めて違いに気づきました。
–どうやって解決したのですか?
拠点でのルールを作りました。
皆さんも快く「ルールを作って間違えないようにしよう!」と、ポジティブな反応で嬉しかったです。そこからは漢方以外のことでも「中国ではどうやっている?」「日本ではこうなんだよ」と雑談を交えて文化の擦り合わせをしています。これはクルー間だけでなく、利用者様ともお話しすることがあり、互いに学び合う機会になっています。
小さな変化に気づき、笑顔が生まれた瞬間

ー嬉しかったことや成長を感じたことはありますか?
利用者様のなかには、障がいの特性上、自分の気持ちを表現することが難しい方もいらっしゃいます。
そんな状況のなかで、利用者様とのコミュニケーションが増え、ちょっとした悩みや気になることを私に相談してもらえると、とても嬉しく感じます。また、何度もコミュニケーションをとっていると、利用者様の様子やちょっとした気持ちの変化に気づけるようにもなってきました。
ー例えば?
私の勤務するグループホームには、車いすを利用されている方が2名いらっしゃいます。移動のしやすさの関係で、これまでは同じ1階フロアで過ごされていました。しかしある時、そのうちのひとりが、別の利用者様の出す音に敏感になってしまい、落ち着いて生活できない日が続きました。そのため、その方は2階へ移ることになったんです。
一方で、そのまま1階に残った利用者様の様子を見ていると、表情や食事量が少しずつ変化し、日に日に元気がなくなっていくように見えました。本人は言葉にしませんが、心の中で何かを抱えているのかもしれない…と感じました。
ーなるほど…
そこで他のクルーにも相談し、「一緒に気分転換に行った方がいいのでは?」と提案しました。
ご本人たちにも確認し、二人とも賛成してくれたので、一緒に散歩に出かけ、途中でコンビニにも寄りました。久しぶりに顔を合わせると、二人ともどこか嬉しそうな表情を見せてくれました。「急に会えなくなる」という小さな変化が、実はストレスになっていたと気づかされました。
私たちも、いつも一緒にいる人と突然会えなくなると「何かあったのかな」「自分のせいかな」と思うことがありますよね。それは利用者様も同じ。こうした何気ない変化に気づくことができ、二人の笑顔が戻った瞬間に立ち会えたことは、とても嬉しかったです。
共通の話題でまずは友達へ。会話の積み重ねが頼られるコツ

ー入社してから帰省はされましたか?
はい。夏に連休をいただき、中国に帰省しました。
自宅に戻るよりも職場から空港に行く方が近いため、職場に荷物を持ってきて、仕事が終わった後にそのまま空港へ向かいました。
ー成田にはそんなメリットがあるんですね(笑)
ー最後に、同じように日本で就職を考えられている方にアドバイスをいただけますか?
私はまず「友達になる」意識で利用者様に接しています。
誤解のないように言うと、馴れ馴れしく接するのではなく、共通の話題を見つけたり、自分から興味を持って話しかけに行っています。私の場合は、その話題がアニメやレトロゲームでした。
ーアニメやレトロゲーム?
昔のゲームを集めるのが好きなんです。
そして利用者様の多くは、そのゲームを現役でしていた世代の方たち。ゲームの内容はもちろん、そこから話が広がって、私がゲームに興味を持ったきっかけや、時には「中国にもあるの?」など母国の文化にも興味を持っていただけ、会話が弾むこともあります。
そこで心の距離を縮めることで、何か不安なことがあったときに相談してくれるような関係性へとステップアップしていけるのかなと感じています。
ー未来の仲間へのメッセージをお願いします
言語、食事、常識、時間の使い方、コミュニケーションの取り方など…
それぞれの国ごとの文化があります。私はこの仕事を通して、日本と母国の文化の違いを学び続けています。
分からなければ聞けばいいだけです。
ドットラインには「違い」を快く教えてくれる仲間がいます。不安な気持ちも分かりますが、コミュニケーションを恐れず行動してみてください。
私は将来、母国でも課題になるであろう障がい者の現状について、現場経験だけでなく、会社の専門研修を通して学びを深めています。日々の経験や知識の積み重ねが、いつか自分たちの未来につながると信じています。
今はまだ海外出身クルーは少ないので、仲間が増えるのを楽しみにしています。